撫子(なでしこ)ってどんな花?
撫子の基本情報
撫子は、ナデシコ科ナデシコ属の総称で、学名はDianthus(ダイアンサス)です。日本にあるナデシコ属の仲間を総称して「ダイアンサス」とも呼びます。カーネーションもダイアンサス属に含まれますが、通常はカーネーションを除いたものを総称して「ダイアンサス」と呼びます。原産地は、アジア、ヨーロッパ、北アメリカ、南アフリカで、北半球の温帯域を中心に約300種が分布しており、たくさんの園芸品種も作りだされているのです。
撫子の種類
カワラナデシコ
本州以南から四国に分布し、日本国外では韓国、台湾、中国に分布する多年草で、花の時期は5月~8月です。別名「ヤマトナデシコ」とも呼ばれます。日当たりのよい草原や山地、また海岸の砂浜にも生息します。花びらに深い切れ込みがあるのが特徴です。
ヒメハマナデシコ
日本固有(日本にのみ自生)の撫子で、九州、沖縄及び本州と四国の一部に分布します。日当たりのよい海岸の砂浜や岩場に生育する多年草です。花の時期は8月から11月です。
ハマナデシコ
本州以西の日本と中国に分布し、別名を「フジナデシコ」「ベニナデシコ」といいます。海岸の崖や砂地に生育する多年草です。花の時期は7月から10月です。

ボタ爺
セキチク
中国が原産でヨーロッパで改良されたセキチクは、別名を「カラナデシコ(唐撫子)」といいます。葉っぱの形が竹に似ていることからこの名前がついたといわれています。花の時期は4月から8月です。
タツタナデシコ
タツタナデシコはヨーロッパ東部から南部にかけて分布するナデシコ科の多年草で、カーネーションなどの園芸新種の親でもあります。花の時期は4月から5月です。
カーネーション
母の日に贈る花として有名なカーネーションは、原産地は不明で、地中海沿岸で栽培されていた種にセキチクなどが交配されて作られた園芸品種です。別名を「オランダセキチク」「オランダナデシコ」といいます。四季咲き性ですが、主に4月から6月に花を楽しめます。
ナデシコオリビア
ナデシコオリビアは草丈が低い、コンパクトサイズの四季咲き撫子です。耐寒・耐暑性があり栽培しやすく、また花径が大きく、秋の花つきも大変よいです。開花時期は3月~7月、9月~10月と比較的長く花を楽しめます。
撫子の特徴
撫子の花はぎざぎざと切れ込みの入った5枚の美しい花びらが特徴です。品種によって切れ込みが浅かったり深かったりしますが、さまざまな交雑や品種改良が行われ、花びらの形は多種多様です。どの種も耐寒性はありますが高温多湿を苦手とするものも多く、やや冷涼な気候を好みます。花の咲く季節は種類によって変わり、園芸品種には四季咲き性のものが多いです。品種や場所によっては、ほぼ周年にわたって花を楽しめるのも特徴です。

ボタニ子
撫子はたくさんの種類や品種があるんですね。では次に、撫子の花言葉をみていきましょう!
撫子の花言葉(全般)
日本での花言葉
日本での撫子の花言葉は「純愛」「貞節」「無邪気」です。小さく可憐に咲く姿が、汚れのない純潔な様子をイメージさせることから、結婚式では花嫁のブーケに撫子の花をいれる女性も多いそうです。また撫子は「源氏物語」の中にも登場しますが「撫子」を幼児の象徴として書かれています。子どもは「無邪気」なものですから、花言葉の由来となったのかもしれませんね。
外国での花言葉
撫子の英語の花言葉は「大胆(boldness)」です。この花言葉の由来はテルスター(西洋ナデシコ)からきています。テルスターの花の色は、赤やピンクですが、その鮮やかな赤やピンクのドレスを身にまとった「大胆」な女性をイメージしたのかもしれませんね。
撫子の色別の花言葉(色別)
赤色の撫子
赤色の撫子の花言葉は「純粋で燃えるような愛」です。情熱的な花言葉は、炎のようないろから来ているのでしょう。
白色の撫子
白色の撫子の花言葉は「器用」「才能」です。白は知的さもイメージさせることから、この花言葉がつけられたのかもしれません。
ピンク色の撫子
ピンク色の撫子の花言葉は「純粋な愛」です。優し気な色合いは、純粋さを表しているようです。
撫子の種類別の花言葉
タツタナデシコの花言葉
タツタナデシコの花言葉は「いつも愛して」です。まるで自分の存在をいつも感じてほしいとアピールしているかのような花姿からきたのかもしれません。
四季咲きナデシコの花言葉
四季咲き撫子の花言葉は「丁寧」です。四季咲き撫子の代表的な花は、テルスター(西洋なでしこ)です。
ムシトリナデシコの花言葉
ムシトリナデシコの花言葉は「罠」「未練」です。赤色のムシトリナデシコの花言葉は「青春の恋」です。
アメリカナデシコの花言葉
アメリカナデシコの花言葉は「伊達男」「勇敢」「義侠」「大胆」などがあります。男性の力強さを感じられる花言葉といえます。
「大和撫子」とは?
植物名としての「大和撫子」
植物としての大和撫子(ヤマトナデシコ)は、撫子の和名である河原撫子(カワラナデシコ)の別名です。日本では秋の七草の一つに「撫子」がありますが、この撫子とはカワラナデシコのことを指しており、古くから日本に自生しています。カワラナデシコは、ナデシコ科ナデシコ属の多年草で、夏から秋の季節にかけて淡紅色の花を咲かせる、高さ30~50cmほどの植物です。
女性を表す「大和撫子」
優しい草姿に可憐な花を咲かせ、香りも魅力的な撫子は「撫でし子」と語意が通じることから、古くから子どもや女性にたとえられてきました。このような由来から『万葉集』でも撫子を歌った歌が26首あり、そのうち8首が愛しい女性を美しい撫子に重ねた歌です。『古今和歌集』などでも、女性の比喩として撫子が使われ、か弱そうにみえながらも心の強さと清楚な美しさをそなえている女性像をいうようになったといわれています。
まとめ
撫子は奥深く、種類や品種も豊富でバラエティーに富んでいることがわかりました。また、日本でも古くから歌に詠まれたりしていることから、それだけ昔から多くの人々に愛されてきた花であることがわかります。また、花言葉もとてもよいイメージばかりで、大切な人へ贈るにはぴったりの花ですね。花を楽しめる時期も長く、比較的育てやすいものが多いので「家のお庭やコンテナで何か植物を育ててみたい!」という初心者の方にもぴったりの花ではないでしょうか。



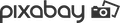














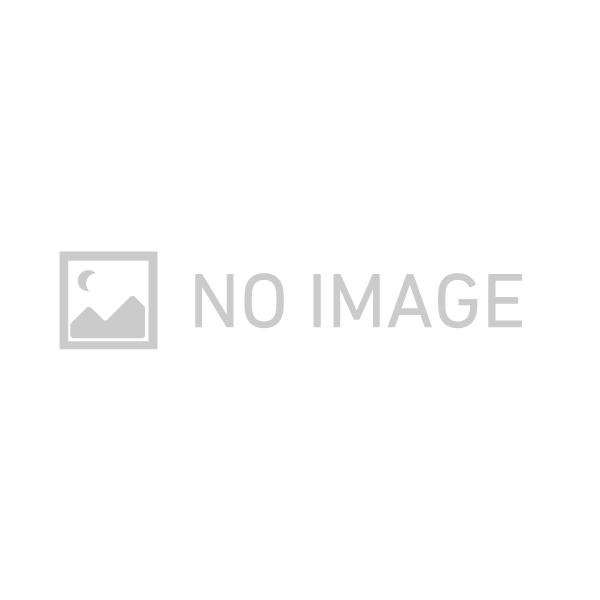




































以上は日本に自生している撫子じゃ。他にもシナノナデシコ、タカネナデシコ、エゾカワラナデシコが日本に自生しとるんじゃ