山や庭に生える赤いキノコ
キノコには「派手な色のキノコは毒があり、地味な色のキノコは食べられる」という言い伝えがあります。しかし、鮮やかな赤いキノコでも食べられるキノコもあり、見た目だけでは毒性の判断できません。キノコは、山林の中以外にも庭や公園など身近な場所にも生えています。赤いキノコの種類や特徴、毒の有無を知りすぐに判断できるようになりましょう。
毒をもつ赤いキノコ
日本には5000種類以上のキノコが生息しており、このうち食べられるキノコが約100種類といわれています。ほとんどの品種が毒キノコか、毒性が判別できない種類です。毒性のある赤いキノコのなかには、水玉模様が特徴的なかわいらしいベニテングタケや、カエンタケのように触れるとかぶれる猛毒の種類があります。
毒キノコ①ベニテングタケ
| 名前 | ベニテングタケ(紅天狗茸) |
| 科名・属名 | テングタケ科・テングタケ属 |
| 環境 | 白樺などカバノキ属の木周辺 |
| 生える時期 | 夏~秋 |
| 毒性 | あり |
ベニテングタケは、白い斑点のある鮮やかな赤いキノコです。アニメのキャラクターに使われるような愛らしい見た目をしていますが、毒をもっています。昔は、強い毒成分をハエの捕殺として利用していました。キノコが輪になって発生する「フェアリーリング」を形成するのが特徴です。幼菌には白い水玉模様があり、成長するとカサが開き白い斑点が消えて赤くなります。
毒キノコ②カエンタケ
| 名前 | カエンタケ(火炎茸、火焔茸) |
| 科名・属名 | ボタンタケ科・トリコデルマ属 |
| 環境 | ブナやクヌギの木など広葉樹林の地上や切り株 |
| 生える時期 | 初夏~秋 |
| 毒性 | 猛毒あり |
カエンタケは、燃え上がる炎のような形をした猛毒キノコで、主に西日本の山で多く見かけられます。強い毒性をもっているため、食用には向いていません。また皮膚に触れただけで毒素が体内に吸収され炎症を起こす危険があります。高さ10~15cmほど成長し、まとまって発生することは少なく単独で生えている場合が多いです。人の手指のように枝別れしており、ふっくらした厚みと硬さがあるのが特徴です。
毒キノコ③バライロウラベニイロガワリ
| 名前 | バライロウラベニイロガワリ(薔薇色裏紅色変) |
| 科名・属名 | イグチ科・ヤマドリタケ属 |
| 環境 | 針葉樹林内の地上や切り株 |
| 生える時期 | 夏~秋 |
| 毒性 | あり |
バライロウラベニイロガワリは、一口で強烈な胃炎を引き起こす毒キノコです。カサの表面はバラのような赤紫色で、裏側と柄は紅色をしています。北海道の寒冷地や本州の高山地帯など限られた場所にしか生えない種類です。フェルト状のカサは、直径5~10cm程度あります。カサや柄を傷つけると傷口が青変(せいへん)するのが特徴です。

ボタニ子
毒キノコ④アカヤマタケ
| 名前 | アカヤマタケ(赤山茸) |
| 科名・属名 | ヌメリガサ科・アカヤマタケ属 |
| 環境 | 林の中や竹藪、草原、ゴルフ場、庭など |
| 生える時期 | 夏~秋 |
| 毒性 | あり |
アカヤマタケは、カサの直径1.5~5cmほどの小さい毒キノコです。強い毒性はありませんが、軽い中毒を起こす場合があります。カサは円錐形をしており、成長しても平らになるまで開くことはありません。赤色のほかオレンジ色や黄色のものも存在し、表面には艶やかなヌメリがあります。手で触れたり、傷をつけたりすると青変します。
毒キノコ⑤ドクベニタケ
| 名前 | ドクベニタケ(毒紅茸) |
| 科名・属名 | ベニタケ科・ベニタケ属 |
| 環境 | 広葉樹林や針葉樹林など、さまざまな林の中 |
| 生える時期 | 夏~秋 |
| 毒性 | あり |
ドクベニタケは、鮮やかな赤色をした毒キノコです。輪を描くように並んで生えフェアリーリングを形成します。カサの直径3~10cm、幼菌のころは饅頭型で成長すると平らに開きます。全体的にもろく、触るとボロボロ崩れるのが特徴です。カサの表面の赤い皮は簡単にはがせて、湿気のある場所ではヌメリがでます。
毒キノコ⑥アカタケ
| 名前 | アカタケ(赤茸) |
| 科名・属名 | フウセンタケ科・ササタケ属 |
| 環境 | 針葉樹林内の地上や切り株 |
| 生える時期 | 夏~秋 |
| 毒性 | あり |
アカタケは、やや大きめの赤褐色の毒キノコです。直径2~5cm程度あり、幼菌時は饅頭型で成長すると雨傘のような形に開きます。表面はパサパサしており粘り気がありません。押しつぶすを赤い汁が出る特徴をもつため、煮汁を使って衣類の染料にする場合があります。毒性をもち、食べられないキノコです。
食べられる赤いキノコ
食べられる赤いキノコは、タマゴタケなど4種類のキノコが有名です。生のまま食べるのは危険です。土やゴミ、ヒダの中の虫を取り除き必ず加熱して食べましょう。
食用キノコ①タマゴタケ
| 名前 | タマゴタケ(卵茸) |
| 科名・属名 | テングタケ科・タマゴタケ属 |
| 環境 | 広葉樹や針葉樹林内、庭、公園 |
| 生える時期 | 夏~秋 |
| 毒性 | なし |
タマゴタケは、卵のような形をした食べられるキノコです。幼菌のころは卵型ですが、やがて饅頭型になり最終的に平らに変形していきます。カサの直径は6~18cmほどで、赤や赤橙色をしています。水玉模様がなくなったベニテングタケに似ているため注意しましょう。カサの開く前の幼菌のほうが旨味があり、汁物や煮物におすすめです。
食用キノコ②オウギタケ
| 名前 | オウギタケ(扇茸) |
| 科名・属名 | オウギタケ科・オウギタケ属 |
| 環境 | アカマツ、クロマツなど針葉樹林内 |
| 生える時期 | 夏~秋 |
| 毒性 | なし |
オウギタケは、直径4~6cmほどの小さい食用キノコです。アミタケの群生のなかに点々と混じるように発生します。カサは饅頭型から平らに開き、なめらかな表面には強い粘りがあるのが特徴です。甘い香りと粘りを活かして和風の汁物や、おろし和えにして食べましょう。
食用キノコ③トキイロヒラタケ
| 名前 | トキイロヒラタケ(朱鷺色平茸) |
| 科名・属名 | ヒラタケ科・ヒラタケ属 |
| 環境 | 広葉樹の枯れ木や切り株など |
| 生える時期 | 初夏~秋 |
| 毒性 | なし |
トキイロヒラタケは、朱鷺(とき)のような美しいピンク色をした食用キノコです。直径が2~14cmほどあり、饅頭型から徐々に開いて貝殻型になります。成長すると色が白く変色し、肉質が繊維質になり食用に向かなくなります。茹でると色が抜けてしまうため、軽く揚げたり炒めたりして彩りに使いましょう。
食用キノコ④カンゾウタケ
| 名前 | カンゾウタケ(肝臓茸) |
| 科名・属名 | カンゾウタケ科・カンゾウタケ属 |
| 環境 | シイなど広葉樹の根元付近 |
| 生える時期 | 春、秋 |
| 毒性 | なし |
カンゾウタケは、肝臓のような形をした平べったいキノコです。直径5~30cmほどの大きさで、成熟すると縁が波をうったような形状になります。幼菌は赤紅色で成長すると鮮やかな赤褐色になり、切ると切り口から赤い汁が出るのが特徴です。山の中よりも公園や神社などの大木に発生します。バターとの相性がよく炒めて食べるのがおすすめです。

ボタニ子
次のページで「毒性のわからない赤いキノコ」を見ていきましょう。



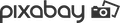

































青変とは、触ったり傷がつくと傷口が青色が変わることです。イグチ科の仲間に多い現象で、インクをこぼしたように青く変色します。