記事の目次
- 1.外来種とは?
- 2.外来種の植物①アメリカフウロ
- 3.外来種の植物②アメリカセンダングサ
- 4.外来種の植物③アメリカオニアザミ
- 5.外来種の植物④アレチウリ
- 6.外来種の植物⑤イヌムギ
- 7.外来種の植物⑥オオイヌノフグリ
- 8.外来種の植物⑦オオカナダモ
- 9.外来種の植物⑧オオアレチノギク
- 10.外来種の植物⑨オシロイバナ
- 11.外来種の植物⑩オニノゲシ
- 12.外来種の植物⑪オランダミミナグサ
- 13.外来種の植物⑫オランダガラシ(クレソン)
- 14.外来種の植物⑬シロツメクサ
- 15.外来種の植物⑭ショカッサイ
- 16.外来種の植物⑮セイタカアワダチソウ
- 17.外来種の植物⑯セイヨウタンポポ
- 18.外来種の植物⑰ハキダメギク
- 19.外来種の植物⑱ハナニラ
- 20.外来種の植物⑲ハルジオン
- 21.外来種の植物⑳ヒメオドリコソウ
- 22.外来種の植物㉑ヒメジョオン
- 23.外来種の植物㉒ホテイアオイ
- 24.外来種の植物㉓ムラサキカタバミ
- 25.外来種の植物㉔ヤナギハナガサ
- 26.外来種の植物㉕ワルナスビ
- 27.まとめ
外来種の植物⑪オランダミミナグサ
水田、荒地、道端などありとあらゆる身近なところに生える雑草のオランダミミナグサも外来種の1つです。オランダミミナグサの原産地はヨーロッパですが、現在は日本だけではなく世界的に帰化植物として分布しています。
オランダミミナグサの特徴
| 学名 | Cerastium glomeratum |
| 分類 | ナデシコ科ミミナグサ属 |
| 原産地 | ヨーロッパ |
| 分布 | 荒地、道端など |
| 花期 | 3月~5月 |
日本へ入ってきた経緯はよくわかっていません。横浜で発見されたのが最初です。とても小さい雑草で、白い花が密集して咲く特徴があります。葉は、上部の葉と下部の葉では違う形をしているのも特徴です。
外来種の植物⑫オランダガラシ(クレソン)
クレソンの名前で知られるオランダガラシも、現在では野生化し外来種となっています。日本で全国的に野生化で見られる植物です。
オランダガラシの特徴
| 学名 | Nasturtium officinale |
| 分類 | アブラナ科オランダガラシ属 |
| 原産地 | ヨーロッパ |
| 分布 | 水辺 |
| 花期 | 4月~9月 |
日本へ入ってきた経緯は食用や薬用としてが始まりです。その後、野生化し全国の水辺で見られる雑草となりました。現在では要注意外来生物に指定されています。半水生の植物なので水耕栽培することも可能です。栽培する場合は、野生化させないように注意しましょう。
外来種の植物⑬シロツメクサ
四つ葉のクローバーや花の冠などで知られる身近で見られるシロツメクサも外来種の1つです。原産地はヨーロッパですが、現在は野生化し日本各地で身近な雑草として親しまれています。
シロツメクサの特徴
| 学名 | Trifolium repens |
| 分類 | マメ科シャジクソウ属 |
| 原産地 | ヨーロッパ |
| 分布 | 野原、道端など |
| 花期 | 4月~10月 |
日本へ入ってきた経緯は、初めに入ってきたのがオランダからの献上品のガラス細工の緩衝材として入ってきたとされています。しかし、帰化する原因となった出来事は、明治時代以降に飼料目的で導入したものが野生化したというものです。葉は、3小葉で花はマメ科特有の蝶のような形をしています。
外来種の植物⑭ショカッサイ
オオアラセイトウ、ムラサキハナナの名前で知られるショカッサイも身近で見られる外来種の1つです。春になると開花し、群生して生えていることもあります。
ショカッサイの特徴
| 学名 | Orychophragmus violaceus |
| 分類 | アブラナ科オオアラセイトウ属 |
| 原産地 | 中国大陸 |
| 分布 | 日本全国の草原 |
| 花期 | 3月~5月 |
日本へ入ってきた経緯は、観賞用・油料用です。その後、戦後には全国的に広がり帰化植物として確認されました。一年草ですが繁殖力が旺盛なため、花が咲き種ができ、種がこぼれると再び同じ場所で芽を出します。
外来種の植物⑮セイタカアワダチソウ
黄色い花をつけ、群生することで知られているセイタカアワダチソウも身近で見られる外来種の1つです。要注意外来生物に指定されている植物でもあります。
セイタカアワダチソウの特徴
| 学名 | Solidago altissima |
| 分類 | キク科アキノキリンソウ属 |
| 原産地 | 北アメリカ |
| 分布 | 河原、空き地など |
| 花期 | 8月~11月 |
日本へ入ってきた経緯は、切り花として観賞用にするためです。その後、野生化や輸入品に紛れ込んできたことなどから全国的に分布が広がっていきました。ほかの植物に影響を与えるアレロパシー作用があるため、同じ場所に生えている他の植物を枯らしてしまうことでも知られています。
外来種の植物⑯セイヨウタンポポ
セイヨウタンポポは、在来種のタンポポとよく似ているため見間違えられることも多いですが、身近に分布する外来種の1つです。また、セイヨウタンポポは在来種のタンポポと交雑することで知られています。
セイヨウタンポポの特徴
| 学名 | Taraxacum officinale |
| 分類 | キク科タンポポ属 |
| 原産地 | ヨーロッパ |
| 分布 | 道端、野原など |
| 花期 | 3月~5月 |
日本へ入ってきた経緯は、飼料などにするためと輸入品に紛れ込んできたとされています。その後、野生化し全国へ広がりました。在来種のタンポポとの見分け方は総苞片が反り返るかどうかです。セイヨウタンポポは反り返っています。
外来種の植物⑰ハキダメギク
ハキダメギクは、道花などでよく見かける外来種の1つです。名前の由来は、日本で見つかったのが世田谷区の掃きだめ(ゴミを掃き捨てるところ)で発見されたので、ハキダメギクという名前が付けられました。
ハキダメギクの特徴
| 学名 | Galinsoga quadriradiata |
| 分類 | キク科コゴメギク属 |
| 原産地 | 北アメリカ |
| 分布 | 日本全国 |
| 花期 | 6月~11月 |
日本へ入っていた経緯は、はっきりとはわかっていません。初めて日本で見つかったのは大正時代だといわれています。花は舌状花であり、小さな花が特徴です。同じ外来種であるコゴメギクによく似ていますが舌状花に冠毛があることで見分けられます。
外来種の植物⑱ハナニラ
白い花で知られるハナニラも身近で見られる外来種の1つです。花壇で育てられていることもあれば、野生化し雑草となってしまっているものもあります。
ハナニラの特徴
| 学名 | Ipheion uniflorum |
| 分類 | ヒガンバナ科ハラニラ属 |
| 原産地 | アルゼンチン |
| 分布 | 花壇、道端など |
| 花期 | 3月~4月 |
日本へ入ってきた経緯は、観賞用として明治時代に入ってきたとされています。その後、野生化し帰化植物として生息しました。ハナニラは球根でもあるため、花期以外では地上部を見ることができないという特徴があります。
外来種の植物⑲ハルジオン
「貧乏草」の名前でも知られるハルジオンは春に花を咲かせます。身近に生えている雑草でもあり、外来種でもあるのです。
ハルジオンの特徴
| 学名 | Erigeron philadelphicus |
| 分類 | キク科ムカシヨモギ属 |
| 原産地 | 北アメリカ |
| 分布 | 道端、野原など |
| 花期 | 4月~8月 |
日本へ入ってきた経緯は観賞用です。その後、野生化し全国へと広がっていきました。ハルジオンによく似た花でヒメジョオンという花がありますが、同じキク科の仲間でありハルジオンは茎の真ん中に空洞があるのが特徴です。




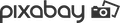























































まだまだあります!次は外来種の植物⑳から紹介します。