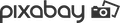剪定は健康な樹木に欠かせない手入れ
剪定と聞くと初めての方は構えてしまうかもしれませんね。ガーデニング歴が長い方なら日常的な植木の手入れとして行っているでしょうが初心者の方は「いったいどこから切ればいいのだろう?」と思うのも当然のことです。この記事では初心者の方に向けて自分で剪定を行うための必要な道具や知識をご紹介していきます。
なぜ剪定を行うのか?
そもそもなぜ剪定を行う理由は以下のようになります。枝の整理を行うことで様々なメリットがうまれます。
剪定を行う理由
- 成長に必要な日差しが木々の隅々まで届くようになるから
- 風などで枝や葉がこすれて傷つくことが減るから
- 風通しがよくなるので病害虫の発生を抑えることに繋がるから
- 見た目にも美しくなり私たちを楽しませてくれるから
庭木の剪定を自分でするメリットは?
庭木の不調に気づきやすくなる
一番のメリットとして庭木の不調に気付きやすくなるという点があげられます。手入れをするとなるとやはり植木に近づくことが多くなり、必然的に日々観察ができるようになります。ちょっとした様子の違いから病害虫による影響や水枯れなどの異変に気付けるようになるので、早いうちに手を打つことができます。
剪定代がかからないので節約になる
2つ目は剪定代がかからないので節約になるという点です。こちらはわかりやすいメリットといえます。ホームセンターなどで頼む場合ですと高さ3mまでの木1本剪定するのに4000円ほどかかります。本格的な植木屋さんや園芸店に頼むとなるとプロの仕上がりが美しいものには違いありませんが料金はさらにかかると思われます。
自然と触れ合いながらいい運動になる
3つ目は自然と触れ合いながらいい運動になるということです。これはガーデニングを楽しむ人なら誰しも実感していることでしょう。きれいな緑や花々を眺め、季節の風を感じながら植木の手入れをするのは気持ちのいいものです。激しい運動ではありませんが頭も体も使い気持ちのよい汗を流せるでしょう。
剪定に必要な道具のご紹介
ではここからは実際に必要な道具を見ていきましょう。初心者の方はまずこれを、といった基本的なものをご紹介してきます。
剪定ばさみ
Mocici 庭のはさみ 庭のはさみ 剪定ばさみ 世帯 粗枝せん断 激しくカット 太い枝カット (色 : Photo Color)
参考価格: 3,729円
色々な価格帯のものが売られていますが、あまりに安いもの(例えば100円均一で売っているようなもの)ですとすぐに刃が切れなくなったり、強い枝に負けてハサミが壊れたりすることもあります。実際に園芸店などで手に取って握った感じがフィットするかなど確かめるのもおすすめです。
ガーデニング用手袋
花柄手袋 ブレス コンフォートグリップ ガーデニング グローブ (3双)
参考価格: 899円
初心者の方がつい忘れがちなのが手袋です。枝に傷つけられたり虫や葉にかぶれたりすることから防いでくれます。ハサミを扱うので自分の手にフィットしたものを選びましょう。
ガーデニングバッグ
Rakuby 折りたたみ ガーデンバッグ キャンバス 再利用 可能 ガーデニングバッグ 防水 ガーデンリーフ 廃棄物バッグ 廃棄物袋ヤード廃棄物バッグ
参考価格: 2,437円
植木屋さんなどプロにお願いすれば切った枝も持ち帰ってくれますが、自分で行う場合はこういったものを一か所に集めてゴミに出す必要があります。画像のような大口のバッグがあると枝も入れやすく運ぶ時も便利です。
初心者でもできる!基本の剪定方法をご紹介
道具がそろったところで次は実際の切り方を見ていきましょう。どれを切ったらいいのかさっぱりわからないという人にもわかりやすく、基本の剪定方法をご紹介します。
まずは忌み枝を切ろう!
枯れ枝などの他にも忌み枝(いみえだ)と呼ばれる枝は切っていきましょう。その種類について詳しくここからご紹介していきます。
①徒長枝
画像を見ても不自然なまでにまっすぐ上に伸びている枝がすぐわかると思います。これが徒長枝(とちょうし)です。主となる枝との境目で切ってしまいましょう。
②立枝
立ち枝ヤベェ(笑) pic.twitter.com/lhzYnQIqYb
— まちゃお (@machao_miyu) March 4, 2018
画像を見ると真ん中の枝がまっすぐ上に向かっているのがわかります。もともとの枝にぶつかってしまっているのも確認できるでしょう。やがて別の枝にぶつかってしまうと思われる時は早めに切っておきましょう。
③逆さ枝
ウチのカエデ
— JW@チューリップ会🌷通常営業 (@J_Wat_a_nabe) July 10, 2019
普通こんな下向きに枝伸びる? pic.twitter.com/jRfDXRCOCa
こちらもわかりやすいでしょう。下に向かって生えている枝のことを指します。画面真ん中の細い枝や右側の長い枝も下に向かって伸びています。このような枝が伸びていった先は地面ですので育っていっても将来性がないことは明らかです。
④平行枝
こちらは初心者が見落としがちです。平行枝という名前の通り、すでにある枝に近い位置で同じ方向に平行に伸びています。画像の真ん中あたりの太い枝の右側に平行して細い枝が確認できます。生えたばかりのころはいいかもしれませんが、やがてこの2本の枝が干渉しあって枝を傷める原因になってしまいます。
⑤からみ枝
先日、剪定のため知人のブルーベリー農園に修業に行ってきました。師の教えを思い出しながら剪定対象枝を探します。細い枝、枯れ枝、さかさ枝、ふところ枝、重なり枝、からみ枝etc. 悩んだら先端を見よ! 迷ったらカットせよ! 調子に乗りすぎ枝がなくなりました...。#牧農場 pic.twitter.com/QysPxWFGtw
— 龍谷大学農学部 (@ryukokuagr) March 5, 2018
名前の通りのわかりやすい切るべき枝です。放置し、絡みながら育っていくと他の枝を傷つけたり日当たりを損なう原因となります。
⑥交差枝
木の声がしたよ。
— のりこ (@25nikoegao25) June 8, 2018
「痛いよ」って。
梅の実がたくさんついて、枝が垂れ下がって、あちこちで交差してた。
だから、
枝が重なりあわないように剪定したいと思います。
そしたら、曇り空だけど空が近くに感じたよ。
風通し、良くしよう🎵
梅の木も人も❤️
淡素🌠 pic.twitter.com/FD5zKenRb5
からみ枝とも似ていますが、交差枝は根本から主となる大きな枝とぶつかるように交差し、斜めに生えてきます。画像を見ても明らかに枝同士があたっているのがわかります。こうした枝は傷の原因となるので切ります。
⑦幹吹き
本日の一枚:幹吹き枝 pic.twitter.com/4M5noqvmbO
— エビ( 💉M💉M💉M 💉pf💉pf #vaccinated) (@ebi_j9) September 25, 2016
幹から直接小枝が出てきている箇所です。葉ばかりが噴き出ている場合もあります。木の風通しを悪くし見栄えもよくないため切ります。
⑧車枝
スーパーで安く安くなってたオカメザクラ、これが車枝というものなのね…と学ぶ。花が終わったら一部切ってあげたらいいのかな。しかしどれくらい切ってよいものかさっぱり。今のうちにもう少し調べてみよう pic.twitter.com/ryuIlNoncz
— いつか (@kotoritrick) March 13, 2019
画像でもわかりやすいでしょう。読み方はそのまま「くるまえだ」となります。一か所から数本の枝がボサボサと車の車輪のように吹き出しているものがそれにあたります。
⑨ひこばえ
主となる枝の隣に出てくる枝で、地面から直接出てきます。栄養を多く奪ってしまいますのでこのひこばえを育てていく予定がない限りは切ってかまいません。
庭木が美しく見える「樹形」を意識しよう
次のポイントはそれぞれの木が持つ「樹形」を意識することです。ハナミズキやヤマボウシなどはきれいな三角形に、ヒメシャラなどシャラはほっそりと上品に、などどういう形にしていきたいかを意識するのがうまくいくポイントです。
実際の切り方を見ていこう
この枝を切ろうと決めた次はどのような切り方にするかを考えます。どのような切り方をするにせよ、切り口が汚いと木にダメージを与えますので切れる剪定ばさみを使い、刃がきちんと枝に当たるようにしましょう。
不要な枝は根元から切る
ここまでご紹介してきたような枝は基本的には根元から切りましょう。根元から切らず、枝の一部を残すような切り方をすると樹形はさらに乱れる上にそこからまた新たな枝や芽がでる恐れがあります。
枝の一部を残す場合は芽の位置がポイント
不要な枝ではないものの、このまま伸びていくと別の枝に当たるような枝は途中で切る方法もあります。外側についている芽が残るように枝を切るとその芽から新しい枝が出てきた場合、木の広がりを作ることにもつながります。
剪定は時期も大切
剪定に大切なのがもう一つあります。それは切る時期です。これを間違えると失敗の可能性も出てきますので適切な時期を見極めましょう。
秋が近づいてきたら強剪定
樹形を整え忌み枝を落とす剪定(強剪定)は春夏は行わないのが無難です。春夏は木の伸びる勢いが強く、剪定を行うことで養分の行き場がなくなった結果、爆発するように枝が次々と吹き出してしまうことがあるからです。このような失敗を避けるためにも春夏にたっぷり日差しを浴びてのびのび育った植木は秋から冬にかけて整えていくのがよいでしょう。
木の根が安定していない移植直後は避けよう
次に気を付けたいタイミングは移植直後です。植木屋さんや園芸店から買ってきて植えたばかりのときや場所を動かした移植直後などはまだ根がしっかりついておらずちょっとした剪定のダメージで枯れてしまうこともあります。このような失敗をしないためにも移植後1年は様子を見るのがよいでしょう。
花を楽しむ木の剪定は特に慎重に
特に花を楽しむ植木の場合は花芽の時期に剪定をするの控えるのがおすすめです。せっかく花芽がついてきたところで枝を切ってしまい、そのシーズンはあまり花が咲かなかったといった悲しい失敗は避けたいものです。
自分で庭木の剪定に挑戦してみよう
剪定はどんな枝を選んで切るべきかイメージがわきましたか?植木屋さんや園芸店でお気に入りの植木を見つけ、自分の庭で毎年少しずつ育てていく楽しみは大きなものです。植木と二人三脚を組むつもりで剪定に挑戦してみませんか?