コーヒーの木のトラブル対処
トラブル①コーヒーの木がかかりやすい病気
コーヒーの木で最も発生しやすい病気はさび病です。春から夏にかけての多湿の時期が要注意。カビ菌が飛散して他の葉に伝染が広がるのを防ぐため、見つけたら感染部分を早め剪定しましょう。念のため、農薬散布をするのもおすすめです。
トラブル②コーヒーの木に害虫が付いてしまった
害虫は冬場の乾燥した時季に発生しやすく、ハダニやカイガラムシ、コナジラミなどが付きます。特に、風通しの悪い室内で栽培している場合は要注意。葉や枝の状態を定期的に確認し、必要に応じて対処するようにしましょう。
ハダニが発生した場合の対処
ハダニは水が苦手なので、風呂場やベランダ、玄関先などで霧吹きを使ってまめに洗い流すのが一番の対処法です。またハダニ専用の農薬を購入し、散布するのも良いでしょう。(ただし、葉に農薬の白い跡が残ることがあるので外観はイマイチ悪くなります。)
カイガラムシが発生した場合の対処
新芽部分や枝の分岐部分にくっついている白くて小さな虫がカイガラムシです。樹液を吸って木を弱らせてしまいますので、手で取り除きます。成虫は動かないので駆除しやすいですが、繁殖が早いのでこまめにチェックすることがおすすめです。白い綿(触るとベタベタ)のようなものはカイガラムシの卵なので、見つけ次第すぐに取り除きましょう。爪楊枝などを使うと作業がしやすいです。
コナジラミが発生した場合の対処
新芽や新葉の裏側が好きな虫です。ウイルス病を媒介するため、場合によってはコーヒーの木が枯れることがありますので、早めの対処が必要です。卵から成虫になる期間が約28日間と短いので増えやすく、農薬を散布しても卵やサナギには効きにくいなど厄介です。見つけた場合はティッシュで拭き取ったり、地道に農薬散布を繰り返して根絶するしかありません。
トラブル③葉の先が茶色くなって枯れる
自然現象なのでそれほど心配する必要はありませんが、観葉植物として見た目が気になる場合は、変色した箇所を清潔なハサミで剪定してもOKです。冬場の寒い環境では葉の変色が多発しますので、冬は木を段ボールや不織布で囲うなど、できるだけ暖かくしてあげましょう。
トラブル④葉の緑色が薄くなってきた
肥料不足が疑われます。即効性のある液体肥料を1週間に1回規定量与えましょう。真夏は逆に株を弱らせてしまいますので、規定量よりも薄くした液肥を与えるようにしてください。室内栽培の場合は日照不足や光合成不良も考えられます。より日当たりの良いところに移動してあげましょう。また光合成にはマグネシウムが必要なので、株元に苦土石灰を撒くのもおすすめです。
トラブル⑤下の葉が変色して落ちてしまう
単に葉の寿命の場合が多いので、特に心配する必要はありません。ただし、ボロボロと大量に落ちるようなら根腐れの可能性が疑われます。時期に関らず鉢から取り出して黒く腐った根を整理し、すっかり枯れる前に清潔な土に植え替えましょう。
トラブル⑥葉焼けしてしまう
コーヒーの木を強い直射日光に当てると葉焼けを起こしてしまいます。観葉植物としても見た目が悪くなってしまうので、葉焼けさせないよう半日陰に置きましょう。冬が明け、春に屋外へ移す場合は、曇りや雨の日、夕方などに日光浴させながら、1~2週間かけて徐々に明るさに慣らしていきます。日光が特に強い6~8月は、他の植物や簾などで影を作ってあげるのも有効です。
コーヒーの木の剪定
コーヒーの木はそれほど樹形が崩れないので、剪定や切り戻しをしなくても栽培できます。ただ、コンパクトに育てたい場合や、枝が広がりすぎてしまった場合などは剪定してもOK。清潔な剪定ばさみで、枝分かれ部分の数ミリ上を剪定します。剪定時期は、生育期前の5月頃か、生育期が終わった10月頃がおすすめです。

ボタニ子
コーヒーの木の植え替え
根が回ったり、鉢底から出てきたりした場合は、一回り大きな鉢に植え替えをしましょう。2~3年に1度が目安です。植え替えに適しているのは生育期前半の5~6月頃。鉢から株を取り出した後、黒く腐った根を整理して古い土を3分の1程度落とし、新たな鉢に植え替えます。植え替え直後はストレスを受けて水を吸わないので、表面が乾かない程度に水をあげ、植え替え後1週間くらい経って株が安定してからたっぷりと水やりをするようにします。

挿し木や、コーヒーチェリーの収穫にもチャレンジしてみましょう。「三大原種」の特徴もご紹介します。次のページへ!










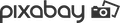





































一部のコーヒー農園では、収穫開始後10年位をめどに根元から30~40cmのところでバッサリと強剪定する「カットバック」を行います。こうして木を若返えらせ、品質向上と収量アップを図ります。