ハゼノキとは
ハゼノキは、ウルシ科ウルシ属の落葉高木です。別名はロウノキ、リュウキュウハゼといいます。果実から木蝋(もくろう)が作られるためロウノキの名前がついたといわれています。また、その蝋作りが琉球王国(現在の沖縄)から伝わったことから、リュウキュウハゼと呼ばれるようになりました。
ハゼノキの特徴
花の特徴
5〜6月頃に枝の先に小さな黄緑色の花を円錐状にたくさん咲かせます。ハゼノキは紅葉や果実に注目されがちで花はあまり目立ちませんが、かわいらしい花です。花言葉は「真心」です。
葉の特徴
葉は羽状複葉(うじょうふくよう)につきます。ハゼノキの葉の形や質感は、ウルシ科のほかの植物であるヤマハゼ、ウルシ、ヤマウルシなどと区別するときのポイントです。どれもよく似ており見分けるのは困難ですが、ハゼノキの葉は硬さがあり細長い形状で、表面に光沢があります。裏表ともに無毛も特徴です。葉の縁は全縁で、鋸歯(きょし)のギザギザはありません。

ボタニ子
果実の特徴
花がついたあと、秋には小さな果実が多数つきます。この果実は脂肪分が多く高カロリーで、カラスなどの野鳥が枝の上で食している姿がよく見られます。ハゼノキの木蝋は、この果実をつぶして作られるものです。
きつねの小判
ハゼノキの果実の中には種が入ってますが、この種は「きつねの小判」または「ネズミの小判」と呼ばれます。「100個集めたら願いごとが叶う」「お金持ちになる」などのジンクスがあり、子どもたちに人気です。ハゼノキの果実を食べた鳥たちによって運ばれる(フンとして排出したものなど)ため、樹が生えていない場所、無関係な場所に落ちてることも多々あります。
ハゼノキの紅葉
ハゼノキは紅葉した姿が大変美しいことでも知られています。晩夏には緑の葉に赤みが混ざりだし、秋にはきれいに赤く色づきます。その美しさから俳句では「櫨紅葉(はじもみじ、はぜもみじ)」と表記され、秋の季語にもなるほどです。
ハゼノキの用途
ハゼノキは元々ロウノキといわれるほど、ロウを採取するための樹として重宝されていました。その用途としてあげられるのは、木蝋の原料でしょう。木蝋はろうそくやワックス、石鹸、クレヨンなどに用いられます。そのほかにも染料や木材としてなど、用途はさまざまです。
木蝋
近年、一般的によく使われているろうそくは洋ろうそくといって、石油から作られるパラフィンが原料です。洋ろうそくは明治時代頃から流通し始めました。それ以前の室町時代から使用されているものが和ろうそくです。ハゼノキを原料としたもので、果実をつぶして絞った木蝋からできています。洋ろうそくより高価ですがそのぶん炎が大きく、煙や液だれが少なく、なにより炎の揺れる姿は趣きがあります。

ボタニ子
ハゼノキの木蝋はお相撲さんの髪をまとめる鬢付け油(びんつけあぶら)にも使われてるよ!
染色
ハゼノキの樹皮、芯材は染料としても利用されています。その利用法の一つに天皇陛下が儀式の際に身につける衣装、黄櫨染御袍(こうろぜんのごほう)があります。こちらを染めている原料がハゼノキです。
黄櫨染(こうろぜん)とは
黄櫨染(こうろぜん)とは、ハゼノキと蘇芳(すおう)を用いて染色したもので、天皇以外が身につけられない特別な禁色です。赤みがかった黄色、茶に近い色合いです。2019年10月に行われた即位礼正殿の儀の際にも、天皇陛下が着用されていました。テレビでご覧になった方もいるのではないでしょうか。

ボタ爺
黄櫨染にはハゼノキ以外にも、近縁種のヤマハゼを使用していたという説もあるぞ!
木材
ハゼノキの芯材は鮮やかな黄色をしており、木材として細工品や工芸品にも加工されています。また、和弓を製作する際の側木に利用されているのもハゼノキです。





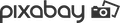










































羽状複葉とは葉軸を真ん中にして、小葉が羽状になっているものです!