保存していた野菜がしなびた!
スーパーや市場、八百屋などで購入してきた野菜をいざ料理しようとしたら、しなしなになっていた経験がある人もいるでしょう。せっかく購入してもしなしなでは美味しくなさそうで、食べてもよいものか迷うかもしれません。しなしなの程度や放置していた場所や長さにもよりますが、野菜をシャキシャキにする方法を知っておくと安心です。
しなびた野菜は捨てるべきか
しなびた野菜を捨てるべきかどうか、はっきりした基準はありません。場所や状態、保存期間などによっても変わってくるからです。自宅へ持って帰ってきてから買ってきたときとの違いで判断するのがよいでしょう。葉や根がしんなりし、軽くしなびているだけの場合は食べられます。筋張っていたり、硬くなっていたりする場合でも腐っていなければ食べられますが、食感が悪いため避けたほうがよいでしょう。
しなびた野菜と腐った野菜の違い
レタスや水菜、ネギなどがしなびるというのは、葉にハリがなくなりしんなりして、シワが寄ることをいいます。腐った野菜は、明らかに色が黄色や茶色く変色し、野菜とは思えない異臭を放ちます。カビが生えたり、触ったときにぬめりを感じたり、さらに溶けたりしていたら、残念ですが復活は無理です。腐っていると判断して早急に捨てましょう。雑菌が繁殖している可能性もあります。
しなびた野菜を復活させる方法
しなびたほうれん草や、ネギ、レタスや水菜など復活させるには、いくつか方法がありますが、状態や大きさ、カットされているかどうかでも変わってきます。ベビーリーフのようにまだ幼いうちにカットされている野菜と、ブロッコリーのように大きいものとでは復活させる時間が違うため、しなびてしまった野菜を観察しながら、時間の様子をみましょう。
水に浸す
簡単なのが水に浸す方法です。しなびたほうれん草、水菜、小松菜、ネギなど、まだしなびている加減が軽度なものに有効です。根がついているようであれば、先を少しだけカットして野菜がもともと生えていた形で、根の部分を水に浸します。2Lのペットボトルの先をカットして花瓶代わりに挿しておくとよいでしょう。

ボタニ子
目安は長くても30分
しなびたほうれん草や、ブロッコリーなどを水につけて復活させるとき、長くても30分程度で水から引き揚げましょう。ネギや水菜、ほうれん草や小松菜などの葉物でしなび具合が軽いものは葉の様子を見て、シャキシャキが戻ってきたようであれば、早めに水から引き揚げてもかまいません。あまり長い時間水に浸しすぎていると、野菜の栄養が水に溶けだす原因になります。
氷水に浸す
もう少し早く野菜をシャキシャキに戻したい場合は、氷水がおすすめです。低温に触れると、野菜の繊維が硬くなり、シャキッとした歯ごたえになります。ベビーリーフやちぎったレタス、ブロッコリースプラウトなども食べる直前、1分~2分氷水に浸してから食卓に並べましょう。
目安は10分~20分
しなびたほうれん草や、小松菜、レタスや水菜なども氷水で復活します。この場合は、10分~20分くらい浸しておきます。ときどき様子を見て、ハリが戻ってきたら水気を切って、新聞紙やキッチンペーパーなどにくるんで保存しましょう。ブロッコリーやカリフラワーなどの大きな野菜は30分前後で様子を見て、氷がなくなっていたら足してください。
お湯に浸す
生の野菜をお湯に浸すと聞くと、少し驚く人もいるかもしれません。これはヒートショックという、野菜を復活させる方法です。収穫される前の野菜は葉の裏にある「気孔(きこう)」という穴で呼吸をしています。しかし、収穫されると水分が抜けるのを防ぐために気孔を閉じてしまいます。ヒートショックは、気孔を開けて野菜に水分を吸収させるための方法です。
お湯の温度は約50℃が理想的です。温度計がない、または測るのが手間な場合は、500ccのお湯を沸騰させたところに同じく500ccの水を足せば約50℃になります。丸い野菜はボウルで、ほうれん草や小松菜、水菜など長細い野菜はバットに入れるとまっすぐ復活します。レタス1枚やベビーリーフなどは1分~2分、丸のままのブロッコリーやカリフラワーは10分~20分くらいが目安です。

ボタニ子
お湯は熱くて触れないほどじゃないけど、ずっと手を入れておくにはちょっと熱いくらいかしらね。やっぱり温度計がほしいわ。
酢と砂糖を加える
お湯で野菜を復活させるときに、1Lのお湯に大さじ1ずつの砂糖と酢を入れるとより効果的です。砂糖が野菜に水分を吸収させるのを助け、酢の殺菌成分でよりハリがでます。この方法も野菜の様子を見ながら、10分~20分浸しておきましょう。しなびた野菜は細胞と細胞の間にすき間が開いています。お湯によってその間のペクチンという成分が硬くなるため、シャキッとした歯触りが復活します。
大根やカブは葉を落とす
カブや大根、ラディッシュや人参などは、葉がついた状態で購入できることがあります。葉にも栄養があり、かさましなどにも使えて経済的のため、捨てずに料理に利用しましょう。葉がついた根菜を保存するときには、葉の根元1cmくらいを切り落とすのがしなびさせないコツです。
収穫後も野菜は生き続けている
野菜は収穫した後も成長し続けています。それは、店頭でも同じで購入したときにも呼吸をして生きています。大根やカブ、人参といった根菜は購入後、葉がついたままでは、食べる部分の栄養を吸い取ってしなびさせてしまうのです。買ってきたらすぐに葉と根を別々に切り分けてから、保存するのがおすすめです。
野菜をしなびさせない保存方法
できれば、購入してきたその日に野菜を料理するのが、栄養も鮮度も保てるので理想的です。しかし、大量に手に入ってすぐには全部食べ切れない場合もあります。野菜の種類によって保存方法も異なりますが、基本的な保存方法を知っておくと、多少しなびてしまっても復活させて美味しく料理できます。
常温保存
野菜の中には冷蔵保存するとかえって傷みやすい種類があります。そんなときは、新聞紙や包装紙を濡らして、野菜をつつんでさらにビニール袋に入れて軽くフタをしておきましょう。風通しのよい、日の当たらない場所が理想的です。それでも、毎日様子を見てしなびてきたら復活させたり、加熱調理をして常備菜にしたりしておくとよいでしょう。
冷蔵保存
冷蔵保存できる野菜もあります。冷蔵庫は野菜ルームと冷蔵室の温度が少し違うため、野菜ルームに保存するのがおすすめです。常温保存のように濡れた新聞紙や包装紙にくるんで、小松菜や水菜など根のあるものは、濡れたティッシュでくるんでビニール袋にいれます。野菜が呼吸できるように、ビニール袋の口を少し開けておきましょう。
いつでもシャキシャキの野菜を食べよう
野菜がたくさん手に入ったとき、しっかり保存したつもりでもいつの間にかしなびてしまうことがあります。しなびてしまったからといって、あきらめなくても大丈夫です。復活させる方法を知っていれば、腐ったりカビが生えたりしないかぎり、いつでも美味しくシャキシャキの野菜を食べられます。野菜をシャキシャキとさせて美味しくたくさん食べましょう。





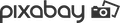




















































ブロッコリーやレタスも茎の下のほうを少し切って、水に浸してあげましょう。丸いボウルを使うとよいわね。